ハードウェアスタートアップの事業創出は、ソフトウェアのスタートアップに比べて難易度が高いです。ハードウェアスタートアップが軌道に乗るためには、最初の試作段階から、開発と事業の両面を考えていくことが鍵となります。
そこで、このページでは、ハードウェアスタートアップの成功に向けた考え方について、当社の過去の知見や経験をもとにご紹介します。
なお、このソリューションに関する当社の製品・サービスは、文末の「JOHNANソリューション」欄に掲載しております。>詳しくはこちら
1.ハードウェアスタートアップの量産・事業化に向けた2つの心得
「量産化の壁」を乗り越えられるかは最初の試作段階で決まる
(1)試作「素早くPDCAサイクルを回して何度もプロトタイピングしよう」
- ハードウェアスタートアップは、事業に関わる製品の試作品を開発し、潜在顧客やVCに試作品を見せてニーズを把握し、改良を続けましょう。
- 試作のポイントは何度も試行錯誤を繰り返し、PDCAサイクルを素早く回して、いかにニーズに見合う製品に発展させていくかとなります。開発自体を外注するという案もありますが、ニーズを試作品に反映できなかったり、思いもよらない不具合の発生などに対応する調整コストが発生します。なるべく、自社で試作品を開発し、改良を続けていきましょう。
- 自社で試作品を開発する場合、すべての専門的な技術やノウハウを持ち合わすことができない場合がほとんどです。自社で全ての技術やノウハウを培うには資金や時間を要するため、大学研究者や協業できそうな企業に相談してアドバイスを得ると良いです。
- 量産段階では手戻りをなるべく避けたいところです。試作段階において量産化を想定した設計を検討しておく必要があります。自社ではなかなか検討できないため、量産化を見据えた製造業者に相談すると、将来的な連携も期待できます。
(2)量産化試作・量産:主体性を持って製造工程を理解し量産に繋げよう
- 量産化試作の段階は、金型などの量産に対応した道具を試作していくため、製品の試作段階のようなプロトタイピングが容易にできなくなります。量産段階の手戻りは試作段階に比べて資金や時間を大幅に費やし、事業継続に影響を及ぼします。
- 量産段階は製造パートナーに量産をおまかせするのではなく、自ら製造工程を理解して量産を委託しましょう。思いもよらない量産になってしまう場合があるため、製造パートナーには具体的に要求を伝えなければなりません。
- ソフトウェアとハードウェアを融合した製品の場合は、検証スピードの違いに注意しましょう。一般的にソフトウェアの方が素早くPDCAを回して品質や価値を向上させることができます。一方、ハードウェアは検証のたびに設計等が必要になり、大きく時間がかかってしまいます。製品開発ルールを作成し、いつの段階で何をしなければならないかを明確にして社会実装を進めていきましょう。
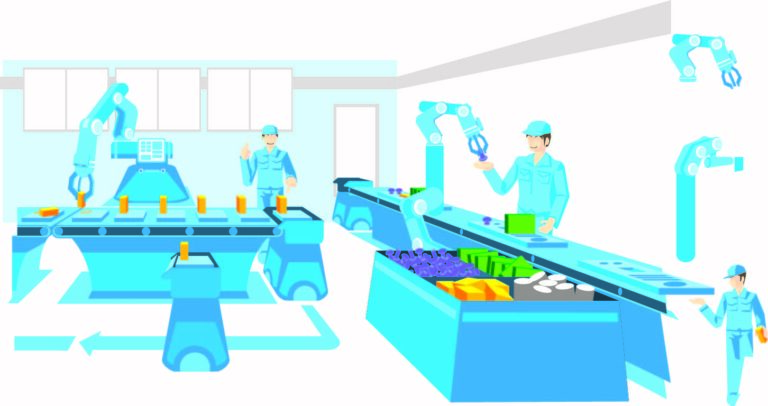
ものづくりをしてビジネスで儲ける
(1)試作品を通じて潜在顧客にアプローチしよう
- 製品のコンセプトが分かる程度の非常に簡単な試作品が完成したら、すぐに潜在顧客やVCにアプローチしましょう。潜在顧客やVCから試作品を通じて具体的なニーズが明らかになり、試作品をすぐに改良しましょう。これを何度も繰り返し、改良を続けましょう。
- 量産化段階では大きな資金が必要になってくるため、これを見据えた資金調達を始めましょう。
(2)素早くフィードバックループを回して受注を獲得しよう
- ハードウェアスタートアップの初期の製品は少数のイノベーターに好まれます。少数のイノベーターと協力関係を築き、PoC(Proof of Concept、概念実証)を短い期間で集中して実施しましょう
- PoCが上手くいけば、その結果を宣伝して広げていきましょう。新たなPoCが受注できるようになり、何度も繰り返していくと大きな受注に繋がる可能性があります。
- ただし、ここで注意する必要があるのは、受託開発のように「ものづくりで儲ける」のではなく、「ものづくりをしてビジネスで儲ける」ことです。ビジネスプランを確立し、短期的な視点かつ長期的な視点で事業開発を進め、事業を成長させていきましょう。
2.事業成功に向けたパートナーとの連携
ハードウェアスタートアップの事業成功に向けては、独創的なアイディアを潜在顧客が求める製品として上市・展開するために、パートナーとの連携が重要となります。ものづくりスタートアップ・エコシステム構築事業(https://startup-f.jp/about/)によれば、平均的なハードウェアの量産のために約20社との提携が必要になっていると言われています。
(1)ものづくりパートナー
- なんでも相談ができる
- 資金面やスケジュールで柔軟な対応ができる
- 試作→量産試作→量産 まで伴走してくれる
- ものづくりノウハウを惜しみなく提供してくれる
- 目先の利益にとらわれない
(2)顧客開拓パートナー
- ターゲット市場・アプリケーションを検討する
- 潜在顧客とのコミュニケーションを橋渡ししてくれる
- お互いの目的に沿ったWin-Win関係を構築する
(3)スポンサー
- VCが経営に大きく口を出さない
- 補助金を活用する
- 金融機関が自社の資金調達がうまくいかなかったとしてもサポートしてくれる
(4)専門家
- 弁理士が主体的に自社の競争力となる知財戦略を確立する
- 士業や業界団体とともにニーズに合った社会のルールを作る
3.JOHNANソリューション
- 当社では1962年創業以来、大手電機メーカーの製造受託を通じて蓄積した技術・経験をもとに、主に電子部品・機器、自動化・省力化機器、医療機器・ヘルスケア関連機器に関する試作から量産までの製品ライフサイクル全般を支援しています。ハードウェアスタートアップに対し、当社技術者によるプロトタイプ試作や量産設計の指導を行い、当社による量産引受けが可能です。
- ハードウェアスタートアップの潜在顧客開拓については、当社のバリューチェーンを活かし、試作段階からの潜在市場・潜在顧客開拓を支援し、技術サポートやAI等アプリケーション開発のサポートも行います。量産試作や量産品では修理やメンテナンスサポートにも対応しているため、スタートアップは商品開発に専念することができます。
- 当社はJAXAとの共同研究や経産省の補助金採択の経験から公的機関の補助事業のアレンジや、VCの紹介も行っております。なお、当社は経済産業省の平成29年度補正予算「グローバル・ベンチャー・エコシステム連携加速化事業補助金(Startup Factory構築事業)」に採択され、ハードウェアスタートアップを支援する体制を整えております。
※画像が見切れている場合は左右にスクロールしてください
事例紹介
-
医療機器・ヘルスケア機器の事例
-
ROV「MOGOOLシリーズ」の事例
-
Startup Factory事業
関連ソリューション
ソリューション
WEB商談も対応可能!製品情報・御見積に関するご依頼・ご質問等お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-63-20250120-63-2025
(平日8:30~17:00)


